京都、花街の一角にひっそりと佇むワインバーバハムート。。
の、お話を今日はお休みして、ちょうど時期ですのでソムリエ試験対策の話を少しばかり。
最初に一応説明しておくと、筆者はソムリエ・エクセレンスの資格保有者です。

ソムリエ歴は22年。
ソムリエ試験を受けたのは12年前で、それまでは資格の必要性を感じていませんでした。
ですが、ワインに詳しいだけのサービスマンとソムリエ資格を持っているのとではやはりゲストからの信頼が違います。何よりバッジをつけておくだけで説明が不要なのが便利。
そんなわけで一念発起して試験を受けることにしたのですが、その時すでに有名なレストランやワインバーでの仕事を歴任してきた手前、不合格など恥ずかし過ぎる!絶対に合格しなければ!という思いで勉強し、見事合格となったのですが、今回はその時の経験を書いていこうと思います。
1⃣ソムリエ協会に入会する。
2⃣ソムリエ教本の購入は最新とその一つ前
3⃣イケてるソムリエ試験対策の教室があるなら入会する。
4⃣勉強を始める前は必ずパブロフの犬をする
5⃣ワインテイスティングの勉強は一次試験合格の後
6⃣サービス実技はポイントをしっかりと!も大事ですがとにかく清潔感を
1⃣ソムリエ協会に入会する。
これにはメリットがめちゃくちゃあります。
僕の場合は1月からソムリエ協会に入会してその年の8月に1次試験を受けたのですが、まず受験の費用が抑えられます。(ソムリエ協会に入会する費用は必要)
その年毎で微妙に変わる試験内容の発表を確認できる。
ソムリエ協会に入会した者にだけ届けられる機関紙「Sommelier」を購読できる。
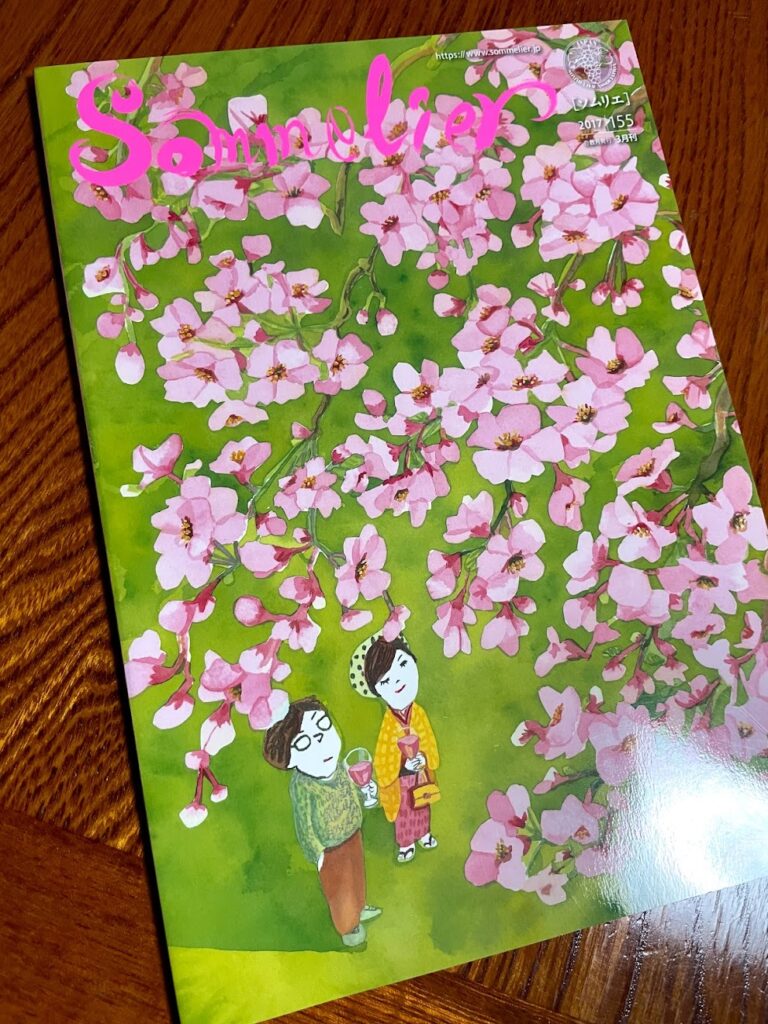
合格したらどっちみち一年はソムリエ協会に入会しなければいけない。
等があります。特に機関紙「Sommelier」の購読は意味合いが大きく、その年の試験内容がその機関紙から引用されることもあります。ただしCBT方式になった今はあまりその期待は望めないかもしれませんが。
どちらにしても機関紙「Sommelier」の購読は現在のワイン界の状況を把握することもできるうえに、二次試験での活躍が見込めます。
ぜひソムリエ協会には入会しておきましょう。
いくらかのお金が必要になりますが、一発で合格できたなら最小限の出費で済みます。
ダラダラと毎年受験をして費用と時間を無駄にすることを考えると一年だけ集中して費用も時間も使ってしまう方が合理的です。
加えて、ソムリエ試験は教育訓練給付制度の対象になりますので費用の20%を後に回収できます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
2⃣ソムリエ教本の購入は最新とその一つ前
ソムリエ試験の大雑把な流れは
7月~8月 一次試験 CBT方式。ようするに座学で、教本を丸覚えが必須。おおよそ7割くらいの正解で合格。
9月 二次試験 テイスティング。ワイン及びワイン以外の何か。 論述。論述は3次試験の合否に直結
10月 三次試験 サービス実技。主にデキャンタージュ。と、二次で受けた論述の結果を合わせて合否
ここで最大の難関が1次の座学だ。
ソムリエ試験を受験するにあたってほとんどの時間がこの1次試験の座学の為に費やされると思っておいてください。二次試験のテイスティングは一次試験終了からで充分に間に合います。
ここで最も重要なアイテムがソムリエ教本です。
試験は必ずこの教本のどこかから出題されます。逆を言うとソムリエ教本を丸覚えしておけば必ず合格します。
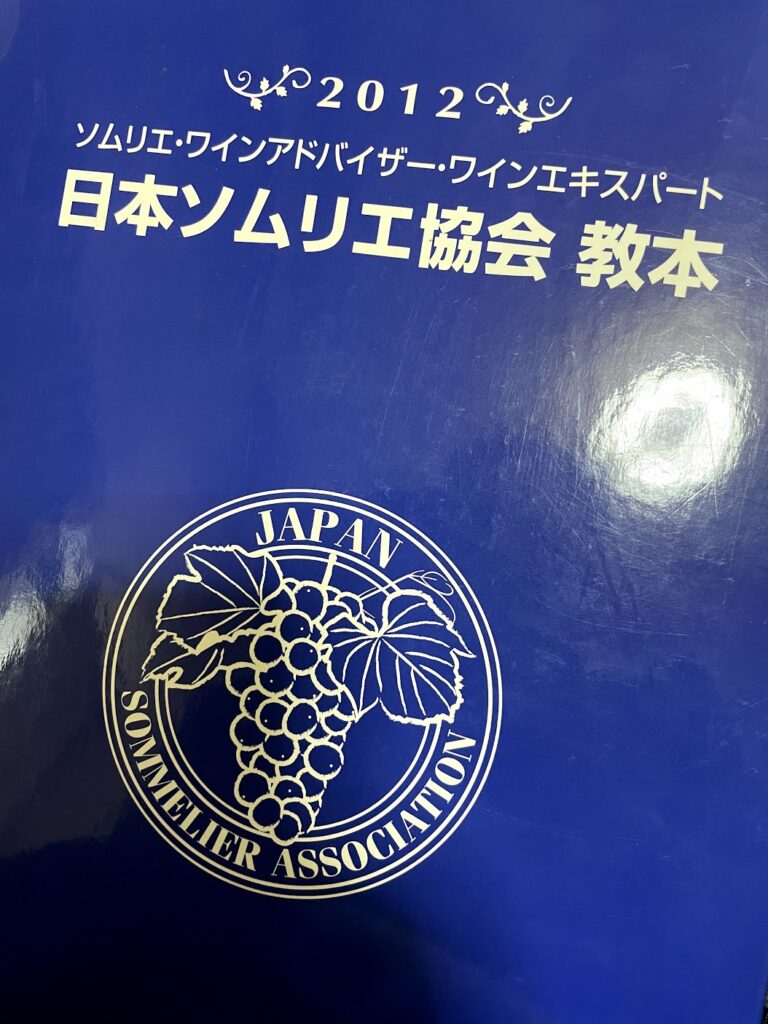
最新のソムリエ教本はだいたい4月半ば頃に発売になり、試験はその8月。
4ヶ月足らずでは心もとないので、それまではその一つ前の教本が教科書になります。
現在のCBT方式の試験ではこの教本をどれだけ熟読しているかが最大の課題です。
7割の正解で合格となるのですが、実際の試験でも7割が基礎問題。残り3割がマニアックな教本の隅っこの方に小さーく書いてある超難関問題がでます。(笑)
なので、合格率を高める為にこの教本の隅っこもしっかり勉強しておく必要があるのです。
そして、この一つ前の教本から新しい教本になった時に情報が改変されているものがあります。
ワインの生産量国別ランク入れ替わったり、カリフォルニア州のワイン法が変わっていたり、フランスで新しいAOCが発表されたり等です。
この「前回から変化のあった箇所」こそが最も出題されやすい傾向にあるので教本が前年分と本年分必要なのです。教本は必ずこの2冊購入して変化した部分を重点的に覚えましょう。
3⃣イケてるソムリエ試験対策の教室があるなら入会する
もうそのまんまです。
しっかりと調べて評価を見て入会を検討しましょう。
京都なら井上塾というところが最適解です。
http://www.inoue-juku.com/
先程の2⃣で述べた古い教本から新しい教本の変化を覚えましょうという話し。実際にそれを調べる作業自体が大変です。こうした教室はその作業をしてくれるので時間が有効に使えます。
こうした塾や教室も厚生労働省の教育訓練制度の対象になるので二割の経費が後に返ってきます。
何より、みんな忙しい仕事の合間を縫って遊ぶのを我慢して勉強している仲間ができるのは心強いものです。
何年も独りでダラダラとやって時間とお金を無駄にするより、しっかりと一年だけの集中と割り切ってお金をこうした教室に使うのは有益です。
4⃣勉強をする前は必ずパブロフの犬をする
これは僕が実際にしていた方法です。
集中力を高め、試験直前の緊張をも和らげてくれるので是非実践してみてください。
方法は簡単です。
まず何でもいいので自分の好きな曲を一つ選んで勉強前に目を閉じてそれを聞きます。
曲の終わりと同時にすぐに勉強を開始しましょう。
次の日もその次の日もです。
この時大事なのは「必ず同じ曲」を聞くことです。
数ヶ月も繰り返せばその曲を聞くと勉強をするというスイッチが入り、自然と集中できるようになります。
しかも試験直前にそれを聞いてから試験に臨めば、今までさんざん勉強をしてきた内容が曲と共に脳の中に流れてきて緊張もほぐれます。
ちなみに僕はソムリエ試験の時は「グリーン」、エクセレンスの時は「宇多田ヒカル」を聞いて集中を高めました。効果的な方法ですのでぜひ実践してみてください。

5⃣ワインテイスティングの勉強は一次試験合格の後
はい。その通りで大丈夫です。
心配な方は今日はもう勉強しないっていう日に酒屋さんで2000円くらいの単一品種のワインを買ってなんとなく飲んでいれば大丈夫です。
ワインテイスティングは国、地域、ブドウ品種を当てることが一つのポイントですが、これは先の座学をしっかりと勉強することで「あれ?これなんとなく日本のメルロぽいな」と思ったらもう長野県塩尻地区のメルロと答えが出ます。
これがフランスのメルロならボルドーのサンテミリオンかポムロールになるみたいな、こうだからこうだという道筋ができるのです。
そういったことも含めまずは座学をしっかりと勉強しておきましょう。
今のCBT方式だと試験が終わった瞬間に合否が解ります。
合格がでたらそこから即テイスティングの勉強に励みましょう。
ワインテイスティングの方法はまた違う場所を設けてアップします。
6⃣サービス実技はポイントをしっかりとも大事ですがとにかく清潔感を。
無事に3次まで進めた方に朗報です。
サービス実技は基本的なことをしっかりとやればまず不合格はありません。
ただし!二次試験時に受験した論述の点数がこの三次試験に加算される為、サービス実技がバッチリでも不合格になることがあります。その場合は論述の方でのミスを疑いましょう。
論述の細かい部分も改めて場所を設けます。
サービス実技のポイントは
はきはきとした声で声量もしっかり。
笑顔!
素早い動きとワインを丁寧に扱う繊細さ
デキャンタージュ後のワインの残量等々。
こちらも細かいことはまた違う場所を設けて書きます。
今回はそういったポイント以上に大事な「清潔」であることについて言及します。
ここで、普段の制服があまりにカジュアルな方は白のシャツに黒いズボン、蝶ネクタイかネクタイ(ネクタイの時はネクタイピンも着用)、清潔な前掛けという格好にしておきましょう。もちろん靴もピカピカにしてください。トーションも自前が必要ですのでしっかりとアイロンをかけたものを使ってください。
僕は以前これが普段の格好だからとめちゃくちゃ汚い靴を履いていたコックさんを試験会場で見かけたことがあります。
その方がどうなったかは解りませんが、僕がお客さんでその靴を履いてる人のサービスを受けたいとは思いません。サービス実技は要するにそういうところを見られています。
まとめ。
ソムリエ試験には最低でも半年から一年の準備期間が必要です。
ただでさえ飲食業は長い拘束時間で働いています。
その上空いた時間を勉強に費やすのは辛いものです。
ですが、何度も書いています通りダラダラと何年も繰り返せば余計にフラストレーションがたまるし時間も費用も余計にかさみます。
一年だけと割り切って最低でも一日3時間の勉強時間を確保し集中して乗り切りましょう。
使ったお金や時間以上の成果がソムリエ資格には必ずあります。
厚生労働省にも認められた職業「ソムリエ」(公的な書類の職業欄に記入できる)
是非とも合格してお客様から「ソムリエさん」と呼ばれましょう!!




